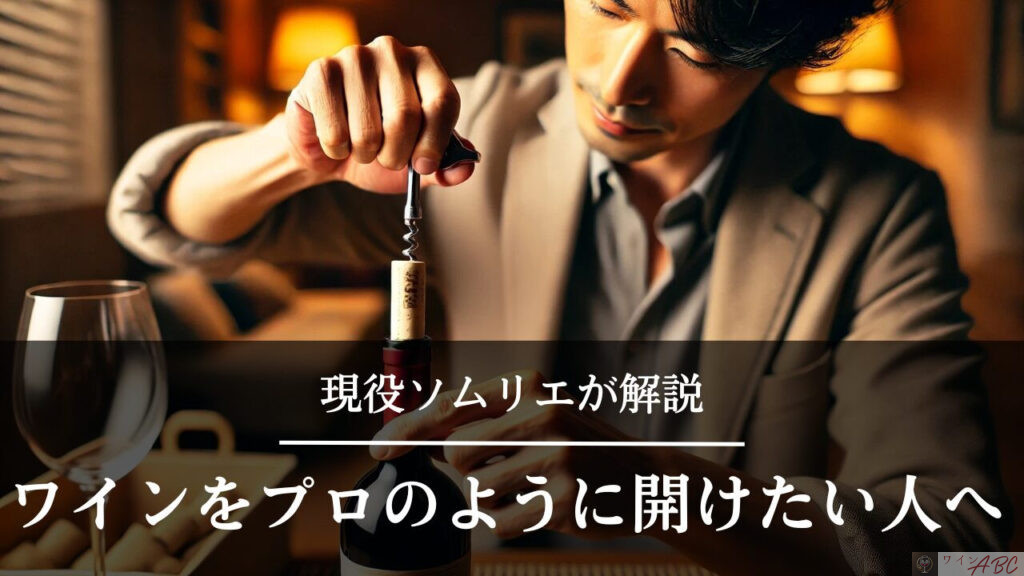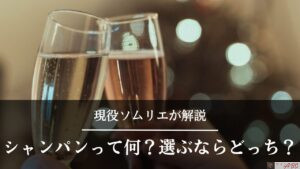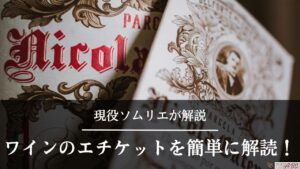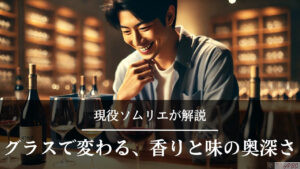子育てや仕事に追われる忙しい毎日の中で、ワインをゆっくり楽しむ時間は特別なひとときです。「ワインを飲むと太る」の噂に不安を感じている人もいます。ワインで太る原因は、アルコールよりも飲み方や食べ合わせです。この記事では、ワインと体重管理の関係を解説し、健康的にワインを楽しむためのコツを紹介します。
記事を読めば、ワインの健康効果を生かしながら、体重を気にせず楽しむ方法がわかります。適量を守り、飲むタイミングや食べ合わせを工夫して、健康的な生活と豊かな時間を両立させましょう。
» ワインの基礎知識から各種ワインの違い、選び方を詳しく解説!

- 夫婦ともに日本ソムリエ協会認定の現役ソムリエ
- 仕事以外でも年間100本のワインを飲む愛好家
- 独自に評価基準を設定し、プロ目線で評価
- 男女それぞれの視点からもワインをレビュー



ワインのプロが、初心者の人にもわかりやすく解説します。
ワインが太ると言われる理由


ワインが太ると言われる主な理由は以下のとおりです。
- アルコール代謝が優先されるから
- 食欲を増進させる可能性があるから
- 高カロリーなおつまみと飲むから
アルコール代謝が優先されるから
ワインを飲むと、アルコール代謝が体内で優先されるため、他の栄養素の代謝が遅くなり太りやすくなります。具体的な影響は以下のとおりです。
- 脂肪燃焼の抑制
- 余分なカロリーの蓄積
- 体重増加のリスク
アルコールの代謝中は、体が他の栄養素を効率的に処理できません。食事から摂取したカロリーが蓄積されやすくなります。ワインと高カロリーな食事を組み合わせると影響がより顕著です。アルコール代謝が優先されると、体重管理が難しくなる恐れがあります。
ワインを楽しむ際は、アルコール代謝による体重増加のリスクに注意しましょう。



アルコールは体にとって、有害なものです。そのため、体は無毒化しようとアルコールを優先に代謝してしまいます。



他の栄養素は後回しにされるので、処理しきれないものは脂肪として蓄えてしまいます。低カロリーなものとの食べ合わせが理想ですね。
食欲を増進させる可能性があるから
アルコールには食欲を増進させる作用があるため、ワインを飲むと太りやすくなると言われています。具体的には、以下の影響があります。
- 胃酸の分泌を促進する
- 血糖値を低下させる
- 食事の味覚を向上させる
ワインを飲むと食欲が増え、普段より多く食べてしまう恐れがあるため注意が必要です。アルコールには自制心を低下させる作用があり、過食につながりやすくなります。アルコールによる脱水で喉の渇きを感じ、食べ物を欲する場合もあります。夜遅くの飲酒は空腹感が増し、夜食のリスクを高めるため注意しましょう。
ストレス解消効果が過食を引き起こす可能性もあります。ワインはさまざまな形で食欲を増進させるため、飲酒時は食べ過ぎに気をつけましょう。
高カロリーなおつまみと飲むから
ワインと一緒に高カロリーなおつまみを摂ることは体重増加の原因になります。チーズやナッツ、オリーブなどはワインと相性が良いですが、カロリーが高い点に注意が必要です。おつまみの摂取カロリーがワインのカロリーを上回ることもあります。以下のおつまみには注意しましょう。
- チーズ(100gあたり約400kcal)
- ナッツ類(100gあたり約600kcal)
- フライドポテト(100gあたり約300kcal)
アルコールの影響で判断力が鈍ると、おつまみを食べ過ぎてしまう場合があります。ワインと高カロリーなおつまみの組み合わせで摂取カロリーが増加します。おつまみの選び方や量を工夫して、体重増加を抑えましょう。生野菜スティックや枝豆など、低カロリーなおつまみを選ぶのがおすすめです。
ワインを楽しみながら体型を維持しましょう。
» ワイン選びの基本からおいしく飲むためのポイントを紹介!
ワインが太ると言われるエンプティカロリーの正体


ワインが太ると言われるエンプティカロリーの正体を以下に説明します。
- ワインとエンプティカロリーの関係
- エンプティカロリーだけでは太りにくい理由
ワインとエンプティカロリーの関係
ワインのエンプティカロリーは体重増加の原因になりますが、適切に飲めば影響を抑えられます。エンプティカロリーとは栄養価のないカロリーのことです。ワインの主なカロリー源であるアルコールは、1gあたり7kcalを含みます。エンプティカロリーは体内で脂肪に変換されにくい性質が特徴です。
ワインの糖質は少なく、エンプティカロリーだけで急激に体重が増えることはありません。過剰摂取や不適切な飲み方が体重増加の原因になる場合があります。エンプティカロリーの影響を抑えるには適量を守ることが重要です。
ワインを楽しみながら健康を保つには、飲む量や頻度を見直し、適切な飲酒習慣を身に付けましょう。ワインを楽しみつつ体重管理も可能になります。
エンプティカロリーだけでは太りにくい理由
エンプティカロリーは栄養素を含まないため、体内で直接脂肪に変換されにくく、太りやすさに直結しないとされています。具体的な理由は以下のとおりです。
- アルコールの代謝が優先される
- 体温を上げる効果がある
- 空腹感を満たしにくい
アルコールは体内で優先的に代謝されるため、他の栄養素の代謝が遅れる場合があります。アルコールには体温を上げ、代謝を促進する効果があるためです。エンプティカロリーは空腹感を満たしにくいため、過剰摂取につながりにくいとされています。
アルコールの代謝には水分が必要なため、適度な水分補給を行うと代謝が促進されます。適量の飲酒であれば、エンプティカロリーの影響は限定的です。エンプティカロリーだけでは太りにくいからといって、大量摂取は適切でないため、適量を守ることをおすすめします。
» ワインの飲み方やマナー、テイスティングの手順を徹底解説!
ワインのカロリーと糖質


ワインのカロリーと糖質に関するポイントを以下に解説します。
- 赤ワイン白ワインのカロリー比較
- ワインと他のお酒のカロリー比較
- ワイン一杯分のカロリーを消費する運動量
赤ワイン白ワインのカロリー比較
赤ワインと白ワインのカロリー差はわずかです。赤ワインは100mlあたり約73kcal、白ワインは約71kcalで、2kcal程度の差しかありません。赤ワインと白ワインのカロリー差が飲酒量に与える影響は限定的です。ワインのカロリーは主にアルコールに由来し、アルコール度数が高いほどカロリーが増えます。
甘口ワインは糖分が多いため、辛口よりカロリーが高くなる傾向があります。一般的なワイングラス1杯(125ml)のカロリーは以下のとおりです。
- 赤ワイン:約91kcal
- 白ワイン:約89kcal
赤ワインはカロリー差がわずかでも、ポリフェノールが多く健康面で優れています。カロリーを抑えるには、ワインの種類よりも飲む量やおつまみに注意することが大切です。適量を守り、ヘルシーなおつまみを選べば、ワインを楽しみながら健康を維持できます。
» 赤ワインと白ワインの違いを知っておいしく楽しもう!
ワインと他のお酒のカロリー比較
ワインのカロリーはビールよりやや高めですが、日本酒や焼酎、ウイスキーよりは低めです。具体的なカロリー比較を以下に示します。
- ワイン(赤・白):約70~80kcal/100ml
- ビール:約40~45kcal/100ml
- 日本酒:約100~105kcal/100ml
- 焼酎:約160~170kcal/100ml
- ウイスキー:約230~240kcal/100ml
一般的に、アルコール度数が高いほどカロリーも高くなります。カクテルのように糖分を含む飲み物は、度数が低くてもカロリーが高い場合があるため注意が必要です。ワインは適度なカロリー帯にあり、他のお酒と比べて選びやすい飲み物です。同量ではビールよりカロリーが高い点に注意し、適量を守って楽しみましょう。
ワイン一杯分のカロリーを消費する運動量
ワイン一杯分のカロリーを消費するには、以下の運動が有効です。
- ジョギング(20分)
- 自転車(30分)
- 水泳(15分)
- エアロビクス(25分)
- ウォーキング(40分)
忙しい共働き夫婦には時間確保が難しい場合もあるため、短時間で効果的な運動を検討しましょう。階段昇降や縄跳びはどちらも15分程度で高いカロリー消費が期待できます。空いた時間に手軽に行えるため、忙しい人にもおすすめです。
スポーツが好きな人には、楽しみながらカロリーを消費できる運動も良い選択です。テニスやゴルフ、ダンスなどが代表的で、友人や家族と一緒に楽しめます。運動にはストレス解消やリフレッシュ効果があります。
ワインを楽しみながら太らない方法


ワインを楽しみながら太らない方法を以下にまとめました。
- 適量を守ってワインを楽しむ
- ベストなタイミングでワインを飲む
- おつまみをヘルシーなものにする
- 低カロリーなワインを選ぶ
適量を守ってワインを楽しむ
ワインを楽しむには適量を守ることが大切です。男性は1日2杯まで、女性は1杯までが適量とされ、1杯は約120mlを指します。基準を守れば、健康的にワインを楽しめます。適量を守る方法は以下のとおりです。
- 週に2日は休肝日を設ける
- アルコール度数の低いワインを選ぶ
- ゆっくり時間をかけて飲む
- 水分を十分に摂取する
- 食事と一緒に飲む
適量を守りながらワインを楽しむには体調に注意し、無理に飲まないことが大切です。飲酒記録をつけると、飲酒量の管理に役立ちます。適量を超えそうな場合は、お酒の誘いを断る勇気を持ちましょう。周囲の理解を得ることで健康を守れます。
ベストなタイミングでワインを飲む
ワインを楽しむベストなタイミングは、食事中または食後です。空腹時の飲酒は避けましょう。食事と一緒に飲むとアルコールの吸収が緩やかになり、食事の味を引き立てる効果があります。食事中の会話を楽しめば適量を守りやすくなります。週末の夕食時や休日のランチ後、特別な日のディナーなどがおすすめです。
就寝前3時間以内の飲酒は避けてください。アルコールが質の良い睡眠を妨げる可能性があるためです。ストレス解消を目的に飲むのも控えるべきです。代わりに、リラックスした時間や運動後に適量を楽しみましょう。飲酒時には水分補給も重要です。飲酒前後に水を飲む習慣をつけると、二日酔いの予防にもつながります。
定期的に休肝日を設けて、健康的にワインを楽しんでください。
おつまみをヘルシーなものにする


おつまみをヘルシーなものに変えると、太りにくくなります。にんじんやきゅうり、セロリなどの野菜スティックをディップと一緒に楽しむのがおすすめです。低カロリーで食物繊維が多く、健康的な選択肢です。
ナッツ類も少量なら良いおつまみになります。健康的な脂肪や栄養素を含みますが、カロリーが高いため小分けにするのがポイントです。低脂肪タイプのチーズを選ぶとカロリーを抑えながら栄養を摂取できます。オリーブやピクルスなどの低カロリーな漬物も手軽でヘルシーです。
生ハムやサラミは薄切りで少量に抑えましょう。魚の燻製や干物、豆腐、枝豆を取り入れるのもおすすめです。フルーツを小さく切って提供すれば、彩りと甘みを加えられます。ワインとの相性も良く、満足感を得られます。ヘルシーでおいしいおつまみを楽しみましょう。
低カロリーなワインを選ぶ
低カロリーなワインを選ぶと、楽しみながら体型維持を意識できます。アルコール度数が低いものを選ぶことがカロリーを抑えるポイントです。ドライなワインは残糖が少ないため、低カロリーでおすすめです。ライトボディのワインはフルボディよりカロリーが低い傾向があります。具体的な種類は以下のとおりです。
- スパークリングワイン
- ロゼワイン
- オーガニックワイン
比較的カロリーが低く、ダイエット中でも楽しめます。飲み方を工夫して、カロリーを抑えましょう。ワインに炭酸水を加えたスプリッツァーにすれば、アルコール度数とカロリーを下げられます。カロリー表示のあるワインを選ぶと、正確なカロリー管理が可能です。



甘口ワインは残糖量が多いため、アルコール度数が低いです。ワインを選ぶ際は、甘口か辛口にも注意しましょう。



白ワインと炭酸水で「スプリッツァー」、赤ワインとジンジャーエールで「キティ」って言うカクテルになりますよ。
ワインがもたらす健康効果


ワインがもたらす主な健康効果は以下のとおりです。
- ポリフェノールによる抗酸化作用
- 心臓病リスク軽減
- 良好な血糖コントロール
ポリフェノールによる抗酸化作用
ポリフェノールは、ワインに含まれる抗酸化物質です。体内の活性酸素を中和して細胞の酸化ストレスを軽減します。老化や病気の予防に役立つとされています。赤ワインに多く含まれており、代表的な成分の一つがレスベラトロールです。レスベラトロールには抗炎症作用もあり、健康維持に役立ちます。
具体的な効果は以下のとおりです。
- 血管の健康維持
- がん予防
- 炎症抑制
血管の健康維持は心臓病リスクの低下につながる可能性があります。がん予防効果は研究が進められており、注目されています。全身の炎症を抑えると、慢性疾患の予防にも効果的です。ポリフェノールの効果を得るには適量を守ることが重要です。過剰なワイン摂取は健康に悪影響を及ぼす恐れがあるため注意しましょう。
心臓病リスク軽減
赤ワインの適量摂取は心臓に良い影響を与えるとされています。ポリフェノールには血管を拡張し血流を改善する作用があり、動脈硬化や心臓病予防に効果的です。善玉コレステロールであるHDLコレステロールを増やし、余分なコレステロールを除去して動脈硬化を予防します。
血小板の凝集を抑え、血栓の形成を防ぐ効果や、抗炎症作用による動脈硬化の進行抑制も期待されています。適量は1日1~2杯程度で、過剰摂取は逆効果となるため注意が必要です。個人の体質や健康状態によって効果が異なる場合もあるため、適切に取り入れることが大切です。
良好な血糖コントロール
適度なワインの摂取は、血糖コントロールの改善に役立つとされています。ワインに含まれるポリフェノールが糖の吸収を遅らせ、食後の血糖値上昇を緩和するためです。インスリン感受性を高めると、長期的な血糖管理の改善も期待されています。具体的には、以下の効果が報告されています。
- 2型糖尿病のリスク低減
- 食後の血糖値上昇の抑制
- インスリンの働きの改善
過度な摂取は逆効果の可能性があるため注意が必要です。効果を得るには食事とともに適量を飲むのがおすすめです。赤ワインは白ワインより血糖コントロールに適しているとされています。
まとめ


ワインを楽しみながら健康的な生活を送るには、適量を守り、飲むタイミングやおつまみの選び方に注意することが大切です。ワインを楽しみつつ体重を管理することも可能です。ポリフェノールなどの健康効果を活用すれば、食生活を豊かにできます。
飲酒の影響には個人差があるため、体調やライフスタイルに合わせて適切に取り入れることが重要です。健康的な生活には、バランスの取れた食事や適度な運動も欠かせません。